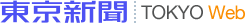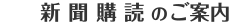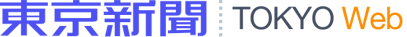<現場から>(3)米軍基地 住民の苦悩はいつまで
2019年7月14日 紙面から
|
滑走路の方向を指し、騒音被害を説明する石郷岡さん=大和市で |
 |
「住民はいつまで苦しい思いをしなければならないのか」。大和市と綾瀬市にまたがる米軍厚木基地のフェンス越しに滑走路の方向を見つめ、近くに住む石郷岡忠男さん(75)が語った。
長年、基地周辺の住民を悩ませる航空機の騒音。石郷岡さんは、騒音解消に取り組む厚木基地爆音防止期成同盟の六代目委員長を務める。約千八百人が名を連ねる同盟は、来年九月で発足六十年。「こんな住民運動が六十年近く続いていること自体おかしい。とっくに国によって解決が図られていていいはずなのに」と無念そうに話す。
旧日本海軍が使用していた厚木基地は、終戦後に米軍が接収。一九五五年ごろから航空機が配備され、七一年に日米共同使用になった。騒音が激化したのは七三年。米空母が横須賀基地(横須賀市)を事実上の母港にし、入港のたびに艦載機が訓練などで飛来するようになった。
その艦載機は、在日米軍再編で約六十機が昨年三月までに岩国基地(山口県)へ移駐。主にジェット戦闘機が巻き起こす一〇〇デシベル(電車のガード下に相当)以上の騒音は九割以上減った。
ただ、米軍ヘリや自衛隊機による七〇デシベル(掃除機と同程度)〜九〇デシベル(パチンコ店内並)台の騒音は二割も減っていない。石郷岡さんは「大きな音に苦しめられる状況に変わりはない。国は騒音が減ったとアピールしたいのだろうが、抜本的な改善には至っていない」と苦言を呈す。
JR相模原駅(相模原市)の北に広がる米軍相模総合補給廠では昨年十月、市民が求める全面返還に水を差す動きがあった。国内三つのミサイル防衛部隊を指揮する新司令部が突如、置かれた。市民団体「相模補給廠監視団」の沢田政司代表(67)は「基地を存続させるための理由付けで、返還の動きをけん制する意味合いが強いのでは」とみる。
周辺住民からは落胆の声が漏れる。「少し返したからもういいという考えでは困る」と憤るのは石井今朝太さん(80)。二〇一四年に約二百十四ヘクタールのうち十七ヘクタールは返還されたものの、全体からすればわずかだ。
基地返還を促す市民協議会の一員として毎年、国に要請してきた石井さんは「こんなにお願いしても通じず歯がゆい」とため息交じりに話す。神奈川は沖縄に次ぐ基地県といわれるのに、参院選で言及する候補者は少ない。石井さんは「広大な基地が地域の発展を阻害してきた。基地と隣り合わせの住民の苦悩に寄り添ってほしい」と願っている。 (曽田晋太郎)